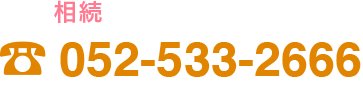- ▶ 相続ってなに?遺言っていつかくの? ▶ 相続っていつから? ▶ 相続で大切なこと ▶ 相続の承認と放棄とは ▶ 相続開始後の手続の流れ ▶ 相続財産とは ▶ 相続人と相続分 ▶ 相続税制の改正 ▶ 遺言とは ▶ 遺産分割手続とは ▶ 寄与分とは ▶ 特別受益とは ▶ 遺留分とは
- ▶ 遺言能力とは ▶ 公正証書遺言作成の際の注意点 ▶ 自筆証書遺言作成の際の注意点 ▶ 高齢者の遺言作成上の注意点
- ▶ 相続の素朴な疑問!Q&A
- ▶ 三輪総合法律事務所の約束 ・人と人とのきずなを守ること ・弁護士にしかできないこと
- ▶ 相続の解決事例集

公正証書遺言作成
 公正証書遺言の要件
公正証書遺言の要件
公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書により作成される遺言のことを言います(民969条)が、遺言者は、公証人の前で、遺言の具体的な内容を口授(くじゅ)し、公証人がその内容を文章にまとめて作成をすることになります。
そして公正証書の作成にあたっては、以下の要件が必要とされています(民969条)。
- ① 証人2人の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭ではなす)こと
- ② 公証人が、遺言者の口授の内容を筆記し、書面にし、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
- ③ 遺言者及び証人が、筆記が正確であることを承認した上で、各自これに署名・押印すること
- ④ 公証人が、証書が適式な方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名・捺印すること
ここで①の証人の立会いについてですが、作成手続の初めから終わりまで、証人2名が立ち会っていなければなりません。途中抜けしたり、途中から参加したりということはできません。
なお、証人の1人が、遺言の筆記が終わった段階から立ち会った事案について、遺言を無効とする判例(最判52.6.1) もありますので注意が必要です。
また、遺言の内容に利害関係を有するかたは、遺言の内容に不当な影響を与える可能性がありますので、証人になることができません。
民法974条2号は、遺言の内容に直接利害関係を有する推定相続人や受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族は、証人として欠格者とされています。
また、未成年者も判断能力が十分でないと考えられますので、欠格者とされています(民974条1号)。
法律相談などで、「遺言をする親の証人に(子である)私がなることができますか。」ということをよく聞かれますが、証人にはなることができないので、別のかたを探す必要があるでしょう。
 口授の要件について
口授の要件について
1口授とは
公正証書遺言で必要となる遺言者による「口授(くじゅ)」は、口頭で言語を持って話すことが必要となります。
口授の要件が要求される趣旨は、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それをそのまま遺言書の内容として表示されることが、遺言者の真意を確保することと考えられることが挙げられます。
病気などで話すことが難しい高齢者のかたが作成した公正証書遺言について、この口授の要件の有無について、争いになることが非常に多いです。
また、ここで口授とは、上記のように、言語をもって申述すること、すなわち口頭で述べることをいいますので、言語以外の表示によるものは口授にはあたらないとされていませんので、注意が必要です。
この点について争われた判例ですが、古いものですが、公証人の問いかけに対し、単に肯定又は否定の動作を行うだけで、わずかに挙動をもって首肯しまたは首を左右に振る程度であったような場合は、口授にあたらないとされています(大判大7.9.9)。
最近の判例ですと、弁護士が関与して作成された公正証書遺言の作成の際に、遺言者が公証人の手を握り、公証人のよる読み聞かせに対し手を握り返したに過ぎない事案について、口授があったとは認められないとされています(東京地判20.11.13)。
また、これは入院中の遺言者のもとへ公証人が訪れ、病院で作成された事例ですが、遺言者が遺言の内容を公証人に説明をしたことがなく、遺言書作成時も公証人の問いかけに声をだしてうなずいたのみの事案で、口授を否定したものもあります(宇都宮地裁平成22年3月1日)。
遺言者が、遺言の内容を話すことができない場合は、公正証書遺言の作成についても慎重にならざるをえませんので、できるだけお元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めしています。
2口授の方法について
では、公正証書遺言で必要とされる口授は、どの程度のレベルで要求されるのでしょうか。
これについては、口授の際、遺言者は、遺言の内容について一言一句すべて口頭で伝える必要はないとされています。
我々に実務においても、遺言者が公証役場に行き、公証人に遺言内容を伝えて、その場で公証人が筆記して、読み聞かせを行うことで公正証書遺言を作成することは希です。
公正証書遺言の作成を依頼された場合は、事前に弁護士が遺言者の意思を法律事務所で聴取して、原稿を作成して、事前の公正証書に確認をしてもらうことがほとんどです。
このような場合、あらかじめ弁護士が作成した原稿を公証人がチェックして、公証人が公正証書を作成しておき、その後に、遺言者の口授を受けて証書の内容と一致することを確認して読み聞かせる、あるいは作成した証書を読み聞かせた後で遺言者がこれを証人するという形で口授をすることも許されるとされています(大判昭6.11.27)。
従って、口授があったと認められるためには、遺言者が遺言の内容の全てを口頭で述べなければならないというものではありません。
少なくとも、公証人が遺言者の口授から遺言の骨子を確認することができるか否かによると考えられます。
我々弁護士としても、遺言者との面談の際は、以上の点を重視して、公正証書作成のお手伝いをさせていただいています。
ただ、遺言者が、遺言の内容を話すことができない場合は、公正証書遺言の作成についても慎重にならざるをえませんので、できるだけお元気なうちに遺言書を作成しておくことをお勧めしています。
 公正証書が見つからない場合
公正証書が見つからない場合
どうも亡くなった方が、生前、公証役場で公正証書遺言を作成していたようなんだけど、ご自宅に遺言が見当たらないといったことがあると思います。
また、被相続人がお亡くなりになり、相続が発生したのに、そもそも遺言を書いていたか分からない、確認をしたい、ということもあると思います。
そのような場合、どうしたらよいのでしょうか。
「公正証書遺言」は、公証人の作成する公正証書により作成される遺言のことを言います(民969条)が、遺言者は、公証人の前で、遺言の具体的な内容を口授(くじゅ)し、公証人がその内容を文章にまとめて作成します。
そして、公正証書遺言の原本は、公証人役場で保管されることになりますので、隠匿されたり紛失することはありません。
公正証書の原本の保存期間は通常20年とされていますが、公証人役場においては、20年経過後も保存する場合もあるそうです。
でも、被相続人が、そもそもどこの公証役場で作成したか分からない場合もあると思います。
そのような場合でも、被相続人が死亡したことを示す除籍謄本と、戸籍謄本や身分証明書等照会をしようとするかたが相続人であることを示す資料をお近くの公証役場に持参し、遺言書の検索を依頼することができます。
検索を依頼する公証役場は、遺言書を作成した公証役場と別の公証役場でも問題ありません。
そして、公証人が日本公証人連合会事務局に遺言の有無を照会してくれますので、被相続人が公正証書遺言を作成したか否か、どこの公証役場で作成したかを知ることができます。
そして、公正証書遺言が作成されていた場合は、公正証書遺言が保存されている公証役場に赴いて、遺言書の謄本を受け取ることができます。
以上のように、公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、紛失する危険がありませんので、このような点も長所であると言えます。公正証書遺言の作成をお勧めしています。
 弁護士から
弁護士から
公正証書遺言は、多少の費用はかかったとしても、偽造や変造、紛失のおそれはなく、公証役場でしっかり保存され、 遺言者の真意をしっかりと正確に相続人らに伝えることができますので、公正証書遺言の作成をお勧めしています。

相続に関するご相談は
私たちにお任せ下さい!
相続問題は、誰にでも、いつか起こりうる問題です。
人と人とのきずなを守ることが私たちの使命です!
もっと詳しく
ご用意させていただきました。

遺言とは?
遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。
相続に強い三輪総合法律事務所が、あなたを全面的にサポートします

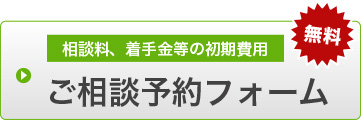
ご相談・ご契約までの流れ

- 弁護士による相談

- 委任契約の締結
ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
ご相談の際には、解決に向けた今後の方針、弁護士費用の目安などについても丁寧にご説明します。ご持参いただく必要資料については、下記のリンクからご確認ください。

ご相談の際に提示させていただく解決への方針、弁護士費用の目安などにご納得いただけましたら、後日ご契約をいただきます。
契約書や委任状等の書類を郵送させていただきますので、ご記入・ご返送をお願いします。問題解決までは長い道のりとなりますが、弁護士とともに頑張っていきましょう。